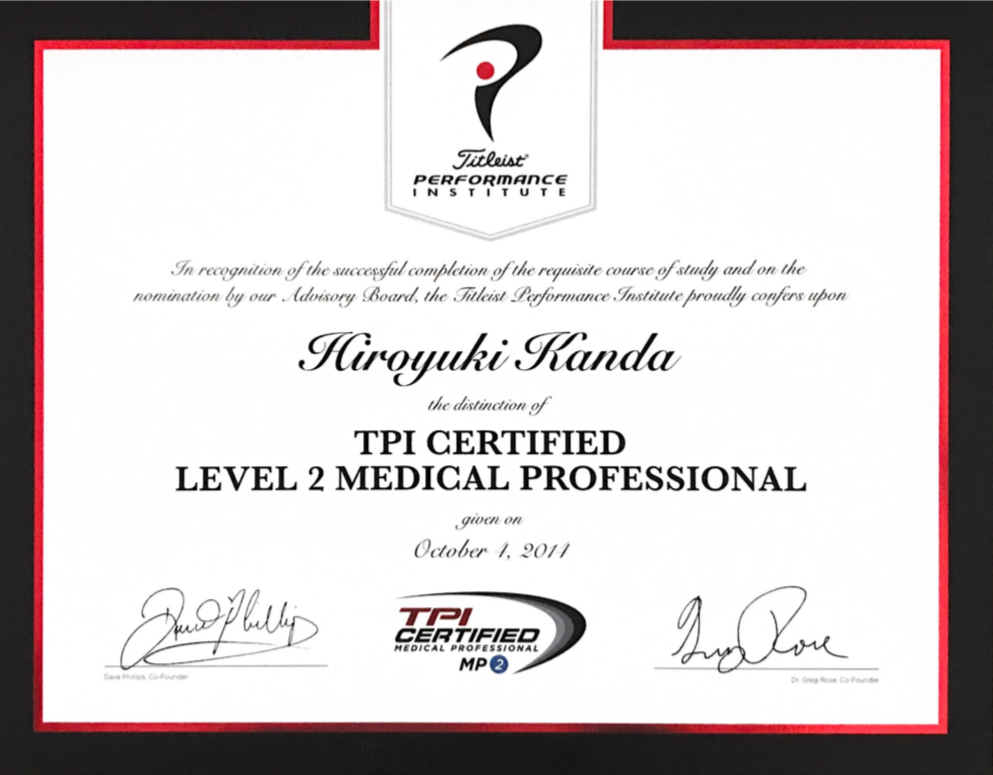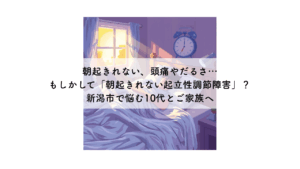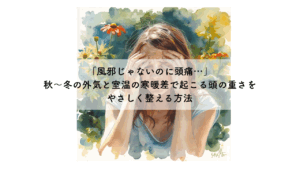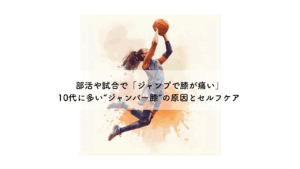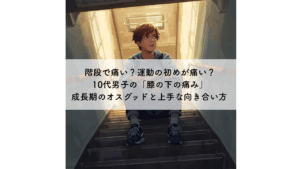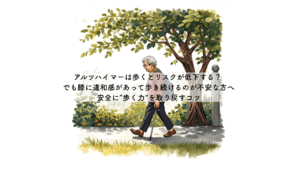こんにちは。新潟市中央区弁天橋通のかんだ整骨院、院長の神田です。新潟市内も紅葉が綺麗になってきましたね
紅葉が綺麗になるにつれ、
「庭の落ち葉掃除をしたあとから肩がパンパンです」
「雪囲いやタイヤ交換の手伝いをしたら、翌日首が回らないくらい肩こりがひどくなった」
といったご相談がぐっと増えてきます。
この時期の新潟は、庭や玄関の落ち葉掃除、雪囲いの準備、カーポートや物置の片づけ、スタッドレスタイヤへの交換など、
どうしても“前かがみ作業”や“重いものを持つ作業”が増えます。
「年齢のせいだから仕方ない」
「運動不足だから我慢しないと」
とあきらめてしまう方も少なくありませんが、落ち葉掃除 肩こりは、体の使い方と寒さの影響を知ることで、負担を減らせる場合が多いと考えられます。
この記事では、
落ち葉掃除や冬支度のあとに肩こりが悪化しやすい理由と、ご自宅でできる対策について、やさしくお話ししていきます。
肩こりの原因とメカニズム

前かがみで腕を前に伸ばす姿勢が続く
落ち葉掃除や冬支度で共通しているのは、
「前かがみで腕を前に伸ばす姿勢」がとても多いことです。
- ほうきや熊手を持って掃く
- ちりとりで落ち葉を集める
- 落ち葉をかき集めてゴミ袋に入れる
- タイヤや鉢植え、雪囲いの支柱を持ち上げて運ぶ
こうした動きをしているとき、気づかないうちに
- 肩が前に入り、胸がつぶれる
- 首が前に突き出る
- 背中が丸くなる
といった姿勢になりがちです。
本来は、股関節や膝も一緒に曲げて、
お尻や太ももの筋肉で体重を支えるのが理想です。
ところが実際には、
- しゃがむより前かがみの方がラクに感じる
- 「少しの作業だから」と同じ姿勢のまま続けてしまう
ことが多く、結果として肩から首だけで頑張る動きが増えてしまいます。
すると、肩甲骨のまわりや首の付け根の筋肉が、ずっと引き伸ばされたまま・力を入れたままの状態となり、作業後に強い肩こりや首こりとして現れやすくなります。
寒さで筋肉が縮こまり、血流が悪くなる
新潟の秋〜初冬は、朝晩の冷え込みが強く、風も冷たくなります。
- 朝の冷たい空気の中で落ち葉掃除をする
- 風が首や肩に直接当たる場所で雪囲いをする
- 手先が冷えて力を入れないと作業が進まない
このような環境では、体は自然と
- 肩をすくめて首まわりを守る
- 肩甲骨の周りの筋肉がキュッと縮こまる
- 手先の冷えを補うため、肩から腕に必要以上に力を入れる
といった反応を起こしやすくなります。
つまり、
「前かがみ姿勢」+「寒さによる力み」 のダブルパンチで、落ち葉掃除 肩こりが悪化しやすい条件がそろってしまうのです。
仕事や家事で疲れた体に“上乗せ”される負担
平日はデスクワークや立ち仕事、家事などで、すでに首・肩・背中に疲れがたまっている方も多いと思います。
そこに休日の庭仕事や冬支度が重なると、
- いつもより長時間の前かがみ姿勢
- いつもより重いものを持つ動作
が一気に増え、「コップから水があふれるように」肩こりが強く出てしまうと考えられます。
「急に肩や首の痛みが強くなった」「回らないくらい固まった」というときは、普段の負担に季節の作業が上乗せされたサインかもしれません。
肩こりの放置リスクと誤解の解消
「そのうち治るから」とガマンしすぎるリスク
作業の翌日くらいであれば、「2〜3日休めばなんとかなるだろう」と思いやすいものです。
しかし、
- 強い肩こりをくり返している
- 毎年同じ時期に同じ場所がつらくなる
- 1週間以上たっても肩・首の重だるさが抜けない
といった状態が続くと、筋肉の硬さだけでなく、姿勢そのもののクセとして定着してしまう可能性があります。
すると、
- 普段のデスクワークや家事でも肩こりを感じやすくなる
- 頭痛や目の疲れ、背中の重だるさなど他の症状につながる
といった広がり方をすることも考えられます。「そのうち治るから」とガマンを続けるより、早めに体の状態をチェックしておく方が、結果的に負担が少なくて済むこともあります。
「強くもめばスッキリ治る」は要注意
肩こりがつらいと「とにかく強くもんでほしい」と感じがちですが、強い刺激をくり返すことで、かえって筋肉が防御的に固くなる場合もあります。一時的にスッキリしたように感じても、
- すぐに元に戻る
- 以前より強い刺激でないと物足りなくなる
といった“いたちごっこ”になることもあるため、
「強くもむ=良い」とは限らないことを知っておいていただきたいです。
落ち葉掃除 肩こりのように、姿勢や寒さ、作業内容が関係している場合は、
- 体の使い方
- 筋肉と関節のバランス
- 日常生活での負担のかかり方
を整理しながら、無理のない範囲で整えていくことが大切だと考えています。
肩こりで自分でできる対処法
ここからは、ご自宅でできるセルフケアを3つご紹介します。どれも特別な道具はいりませんので、できそうなものから試してみてください。
1. 作業前の「肩まわりウォームアップ」
- 目的: 作業前に肩甲骨まわりを温めて動かしやすくし、作業中の肩こりを軽くするため。
- 手順:
- 室内で背筋を軽く伸ばして立つか座る。
- 両肩を耳に近づけるようにギューッとすくめ、3秒キープ。
- ストンと力を抜いて肩を下ろす。これを3〜5回くり返す。
- そのあと、肩を大きく前回し・後ろ回し、それぞれ10回ずつゆっくり行う。
- 注意点: 痛みが強い方向には無理に回さないようにしてください。 呼吸を止めず、ゆっくり息を吐きながら動かすと、筋肉がゆるみやすくなります。
- 所要時間目安: 1〜2分程度。庭に出る前の“ひと手間”として習慣にすると効果的です。
2. 作業の合間の「背伸び&胸ひらきリセット」
- 目的: 前かがみ姿勢が続くことで丸くなった背中・胸まわりをリセットし、肩こりの悪化を防ぐため。
- 手順:
- 10〜15分作業したら、一度ほうきや道具を置いてまっすぐ立つ。
- 両手を組んで頭の上に持ち上げ、ゆっくり背伸びをする。3呼吸キープ。
- 次に、両手を背中側で組み、胸を軽く開くようにして肩を後ろに引く。これも3呼吸キープ。
- 注意点: 反り腰になりすぎないよう、おへそを少しだけ背中側に寄せる意識で行ってください。 ふらつきが心配な場合は、壁や柱の近くで行うと安心です。
- 所要時間目安: 30秒〜1分程度。こまめに体勢を変えることが、結果的に体を守る近道になります。
3. 作業後〜就寝前の「胸と首をゆるめるケア」
- 目的: 作業で固まった胸・首・肩まわりの筋肉をゆるめ、翌日のガチガチ感を軽くするため。
- 手順:
- 入浴後など、体が少し温まっているタイミングで行う。
- 壁の横に立ち、伸ばしたい側の手のひらを壁につける(肩の高さ)。
- その手を壁につけたまま、体をゆっくり反対側にひねり、胸の前側がじんわり伸びるところで10〜15秒キープ。左右交互に2〜3回。
- その後、椅子やベッドに座り、背筋を軽く伸ばしてから、首を前・後ろ・左右にそれぞれゆっくり倒す。痛くない範囲で、1方向につき5〜10秒。
- 注意点: 痛みやしびれが強くなる場合は無理に続けないでください。 呼吸を止めず、「気持ちいい〜少し伸びる」くらいの強さで十分です。
- 所要時間目安: 全体で3〜5分程度。就寝前の習慣にすると、翌朝のこわばりが変わってくることが期待できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 落ち葉掃除で肩こりがひどくなった場合、どのくらい様子を見てもいいですか?
A1. 軽い筋肉痛程度であれば、2〜3日で少しずつ軽くなっていくことが多いと考えられます。ただし、1週間以上たっても肩や首の重だるさがまったく変わらない場合や、回を重ねるごとに症状が強くなる場合は、一度専門家に体の状態をみてもらうことをおすすめします。
Q2. かんだ整骨院では、落ち葉掃除や冬支度がきっかけの肩こりにどのような施術をしますか?
A2. 当院では、神経の反射を活用した優しい施術を中心に行い、バキバキと音を鳴らすような矯正や「その場だけ気持ちいい」強いもみほぐしは行っていません。肩だけでなく、首・背中・骨盤のバランスや、体の使い方のクセもあわせて確認し、お一人お一人に合わせた施術とセルフケアをご提案します。
Q3. どのくらいの頻度で通えば良いですか?
A3. 肩こりの程度や、普段のお仕事・生活スタイルによって適した頻度は変わります。最初のうちは週1回程度で体の土台を整え、その後は状態に応じて間隔をあけていくケースが多いです。初回のカウンセリング時に、現在の状態とご希望を伺いながら、一緒に通院ペースの目安を決めていきます。
Q4. 整形外科や病院に行った方がよいのはどんなときですか?
A4. 肩こりに加えて、手や腕のしびれ、力が入りにくい、強い頭痛やめまいを伴う場合などは、首の骨や神経のトラブルが隠れている可能性もあります。そのような症状があるときや、不安が強いときには、まず整形外科などの医療機関での検査を受けていただくことをおすすめしています。
まとめ

- 落ち葉掃除 肩こりは、前かがみ姿勢と寒さによる力みが重なり、肩〜首・肩甲骨まわりの筋肉に大きな負担がかかることで起こりやすくなります。
- 「年齢のせい」とあきらめる前に、作業前の準備運動・作業中のこまめな姿勢チェンジ・作業後のケアを取り入れることで、つらさを軽くできる可能性があります。
- 1週間以上続く強い肩こりや、しびれ・頭痛を伴う場合には、無理をせず専門家や医療機関に相談することが大切です。
ブログを最後まで読んでいただきありがとうございます。読んで実践していただいたにもかかわらずまだお悩みが残る場合は、きっとセルフケアだけでは手が届かない、身体の奥に原因があるサインです。
一度、私たち専門家にご相談いただくことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。あなたの状態に合わせた治療で、精一杯サポートさせていただきます。
【監修:柔道整復師 神田博行】
電話
TEL 025−211−9541
『ホームページを見て!』とお電話ください。
インターネット予約
24時間いつでもご予約が可能です。
※当日ご希望の方は、お電話にてお願いいたします。
クリック後に予約サイトへ移動します。
LINEからのお問い合わせ
LINE公式アカウントから、お友達追加の後に、フルネームとご用命をお知らせください。
キャンセルについて
当院は完全予約制です。お一人おひとりの施術時間を確保するため、ご予約枠は他の方のご予約をお断りして準備しております。
そのため、直前・当日のキャンセルや無断キャンセルについては、下記のとおりキャンセル料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。
ご予約の変更・キャンセル方法
ご予約の変更/キャンセルは、分かった時点でお早めにご連絡ください。
- お電話:営業時間内
- 留守電/SMS(またはLINE):営業時間外も可(確認後、当院より折り返しします)
キャンセル料について
- 前日までの変更・キャンセル:キャンセル料はかかりません
- 当日のキャンセル(初診):初診料 9,800円をキャンセル料として頂戴します
- 当日のキャンセル(再診):施術料 7,000円をキャンセル料として頂戴します
- 無断キャンセル:ご予約メニューの料金(初診 9,800円/再診 7,000円)をキャンセル料として頂戴します
※「当日」とは、ご予約日(0:00〜ご予約時刻)を指します。
※体調不良などやむを得ない事情の場合も、まずはご相談ください。
遅刻について
遅れることが分かった時点で、必ずお電話またはメッセージでご連絡ください。
ご予約状況により、施術時間の短縮または別日への変更をご案内する場合があります。
また、ご連絡がなく一定時間が経過した場合は無断キャンセル扱いとなることがあります。
お支払い方法(キャンセル料)
キャンセル料は、原則として
- 次回ご来院時にお支払い または
- お振込み等(ご希望に応じてご案内) でお願いしております。
ポリシーの見直し
予約枠の確保とサービス維持のため、内容は予告なく変更する場合があります。
参考文献
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「肩こり」
- 日本整形外科学会「頚椎症性神経根症・頚椎症性脊髄症」
- 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「運動器の加齢変化と痛み」