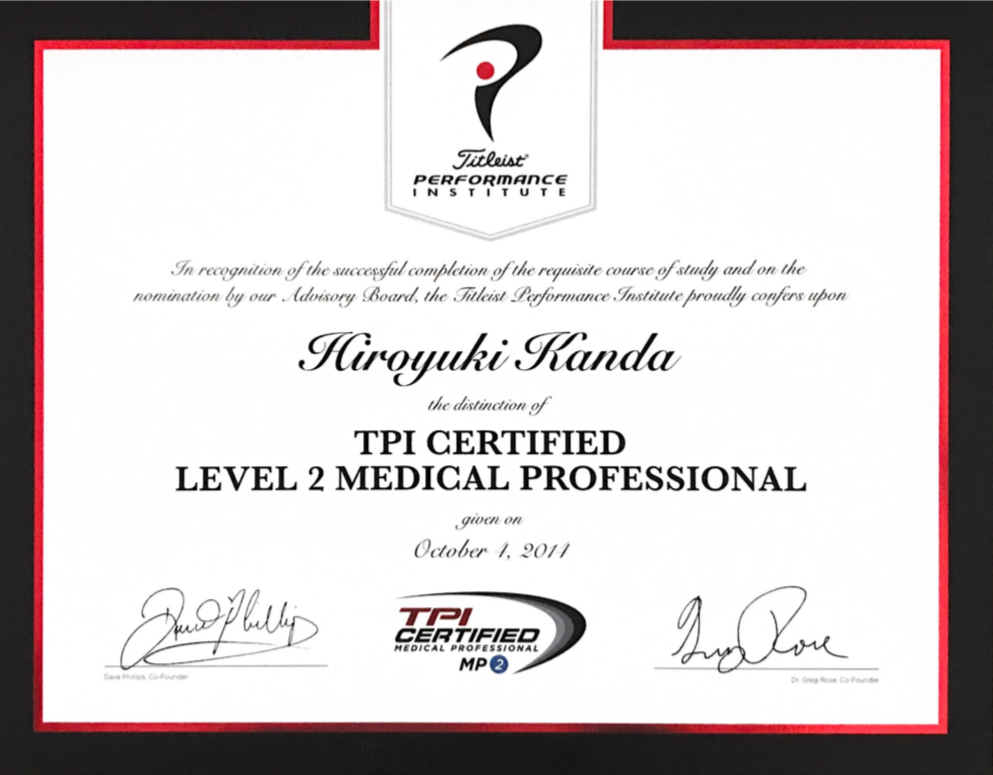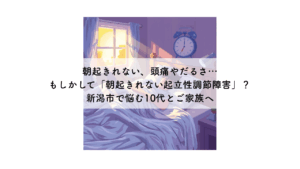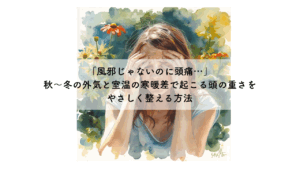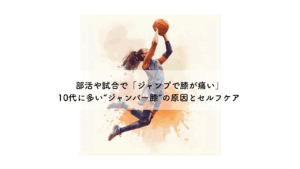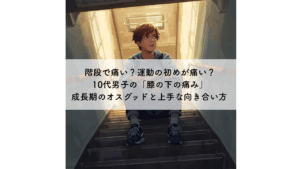こんにちは。新潟市中央区弁天橋通のかんだ整骨院、院長の神田です。
「朝までグッスリ眠りたい」——夜中に何度も目が覚める、布団に入っても考えごとが止まらない、起きたのに疲れが残る……秋口はこんなお悩みが増えます。日照時間の短さ、寒暖差、仕事や家庭の区切りが重なり、**自律神経(交感神経と副交感神経)**がゆさぶられやすい季節だからです。
当院では、体の歪みや姿勢、呼吸、生活リズムをやさしく整え、寝つきと中途覚醒の負担を減らすサポートを行っています。ここでは、できるだけ専門語を避けて、仕組みの整理と“今夜から試せる整え方”をお伝えします(病名の診断が必要な場合は医療機関の評価をご検討ください)。
原因とメカニズム
睡眠は「脳とからだの段取り」で決まります。朝までグッスリ眠りたいのに難しくなる要因は、次のように重なりやすいと考えられます。
1) 自律神経のアンバランス(交感神経の張りつめ)
忙しさやストレス、夕方以降のカフェイン、遅い時間の強い光やスマホ刺激で、交感神経が“活動モード”のまま下がり切らず、寝つきが遅れる/眠りが浅い/夜中に目が覚めるにつながります。
2) 体内時計(概日リズム)の“後ろ倒し”
秋は朝の光が弱く、起床後の「太陽の合図」が不足しがち。結果として眠気と覚醒のスイッチがずれ、朝ボーッとする→昼にカフェインが増える→夜に冴えるという連鎖が起きやすくなります。
3) 姿勢と呼吸の質(体の歪みの影響)
デスクワークやスマホで頭が前に出る姿勢が続くと、胸が縮こまり呼吸が浅くなります。浅い呼吸は“休む神経(副交感神経)”のはたらきを引き出しにくくし、寝床に入っても心身が落ち着かないと感じやすくなります。
4) 生活の微差(寝室環境・行動習慣)
寝室の温度・湿度、寝具の硬さ、就寝前の情報量、夜間のトイレ対策、遅い時間の運動・入浴の仕方など、「ちょっとしたズレ」の積み重ねが、中途覚醒の回数を左右します。
いびきが強い/日中の強い眠気/脚のむずむず(夕方〜夜)/寝言・寝ぼけ行動が多い/2週間以上つづく抑うつ感——こうした場合は、まず医療機関(睡眠医療・耳鼻科・精神科・心療内科等)での評価をご検討ください。
放置リスクと誤解の解消
**「眠れない→不安→さらに冴える」**という循環に入ると、脳疲労が蓄積し、集中力・判断力・痛みの感じ方にも影響します。よくある誤解をやさしく整理します。
- 「寝酒なら早く眠れる」:寝つきは早くても、眠りが浅く分断される傾向があり、早朝覚醒を招きやすいです。
- 「休日にまとめて寝て取り返す」:起床が遅れるほど体内時計は後ろ倒しに。毎日の起床時刻の安定が第一です。
- 「ストレッチだけで必ず解決」:伸ばすことは助けになりますが、光・行動・姿勢・寝室環境のセット調整が戻りづらさにつながります。 当院はバキバキする矯正や“その場かぎり”の強いもみほぐしは行わず、神経の反射を活用した優しい施術で、からだが自分で整う土台づくりを目指します。必要に応じて医療機関とも連携します。
自分でできる対処法
以下は道具いらず・短時間で実践できます。痛みや体調に合わせ、量や強度は無理なく調整してください。
〔朝:太陽と“胸ひらき呼吸”でスイッチを前へ〕
- 目的:体内時計を前にそろえ、日中の眠気と夜の冴えを整える。 - 手順:1) 起床30分以内に窓際または屋外で5〜15分自然光を浴びる(曇天でもOK)。2) 立位で鎖骨を左右に広げる意識で胸を1cmだけひらく→鼻から4秒吸って6〜8秒吐くを5呼吸。3) 白湯や温かい飲み物で胃腸を起こし、5〜10分の軽い散歩ができると理想的。 - 注意点:目の病気の治療中は主治医の指示に従う。強い寒さの外気は防寒を。 - 所要時間目安:合計5〜15分。
〔日中:60〜90分ごとの“姿勢リセット+思考休憩”〕
- 目的:交感神経の張りつめをこまめに下げ、夕方の疲れ溜めを防ぐ。 - 手順:1) イスで坐骨を感じ、骨盤を小さく前後に5回ゆらしてニュートラルへ。2) みぞおちをやさしく前へ、肩はすとんと下げ、顎は1cm引く。3) 20秒だけ窓の外の遠景を見るか、呼吸を3サイクル数えて思考を中断する。 - 注意点:胸を張りすぎて腰を反らさない。焦りが出たら回数を減らす。 - 所要時間目安:1回1〜2分(60〜90分ごと)。
〔就寝前:減光・ぬる湯・“ゆらぎ呼吸”で着地する〕
- 目的:脳の覚醒を静め、寝つきと中途覚醒の負担を減らす。
手順:1) 就寝1時間前から画面と照明を一段落とす(間接照明が理想)。2) 体温より少し高いぬるめの入浴10〜15分か足湯。3) ベッドで4秒吸って6〜8秒吐く“ゆらぎ呼吸”を6回、その後は楽な自然呼吸に任せる。
注意点:寝酒・就寝直前のカフェイン・激しい筋トレは避ける。熱すぎる入浴は却って冴えやすい。
所要時間目安:合計15〜25分。
※環境の工夫:寝室は暗く・静かに・涼しめを基本に(エアコンの風は体へ直撃させない)。枕は首のカーブを埋めすぎない高さをタオルで微調整。夜間トイレが気になる方は、就寝2〜3時間前からの水分量を少し減らし、夕食の塩分も見直しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. どのくらい通えばよいですか?
A1. まずは週1回を2〜4週ほど。日中の眠気・寝つき・夜間覚醒の変化を見ながら、セルフケアと生活リズムが回り出したら間隔を調整します。
Q2. 施術は痛くありませんか?
A2. 当院は神経の反射を活用した優しい施術が基本です。バキバキする矯正や“その場かぎり”の強いもみほぐしは行いません。姿勢・呼吸・寝室環境まで一緒に確認します。
Q3. どんな人に向いていますか?
A3. 夕方から冴えやすいデスクワークの方、交感神経が張りつめがちな方、夜勤やシフト勤務で体内時計が乱れやすい方、季節の変わり目に眠りが浅くなる方に向いています。いびきや無呼吸の兆候があれば医療機関と併行をおすすめします。
まとめ
- 朝までグッスリ眠りたいを妨げるのは、自律神経の張りつめ・体内時計の後ろ倒し・姿勢と呼吸の浅さ・環境の微差が重なるためだと考えられます。
- 朝の光+胸ひらき呼吸/日中の姿勢リセット/就寝前の減光・ぬる湯・ゆらぎ呼吸を、小さく・こまめに積み重ねましょう。
ブログを読んで実践していただいたにもかかわらず、まだお悩みが残る場合は、きっとセルフケアだけでは手が届かない、身体の奥に原因があるサインです。
一度、私たち専門家にご相談いただくことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。あなたの状態に合わせた治療で、精一杯サポートさせていただきます。
【監修:柔道整復師 神田博行】
電話
TEL 025−211−9541
『ホームページを見て!』とお電話ください。
インターネット予約
24時間いつでもご予約が可能です。
※当日ご希望の方は、お電話にてお願いいたします。
クリック後に予約サイトへ移動します。
LINEからのお問い合わせ
LINE公式アカウントから、お友達追加の後に、フルネームとご用命をお知らせください。
キャンセルについて
当院は完全予約制です。お一人おひとりの施術時間を確保するため、ご予約枠は他の方のご予約をお断りして準備しております。
そのため、直前・当日のキャンセルや無断キャンセルについては、下記のとおりキャンセル料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。
ご予約の変更・キャンセル方法
ご予約の変更/キャンセルは、分かった時点でお早めにご連絡ください。
- お電話:営業時間内
- 留守電/SMS(またはLINE):営業時間外も可(確認後、当院より折り返しします)
キャンセル料について
- 前日までの変更・キャンセル:キャンセル料はかかりません
- 当日のキャンセル(初診):初診料 9,800円をキャンセル料として頂戴します
- 当日のキャンセル(再診):施術料 7,000円をキャンセル料として頂戴します
- 無断キャンセル:ご予約メニューの料金(初診 9,800円/再診 7,000円)をキャンセル料として頂戴します
※「当日」とは、ご予約日(0:00〜ご予約時刻)を指します。
※体調不良などやむを得ない事情の場合も、まずはご相談ください。
遅刻について
遅れることが分かった時点で、必ずお電話またはメッセージでご連絡ください。
ご予約状況により、施術時間の短縮または別日への変更をご案内する場合があります。
また、ご連絡がなく一定時間が経過した場合は無断キャンセル扱いとなることがあります。
お支払い方法(キャンセル料)
キャンセル料は、原則として
- 次回ご来院時にお支払い または
- お振込み等(ご希望に応じてご案内) でお願いしております。
ポリシーの見直し
予約枠の確保とサービス維持のため、内容は予告なく変更する場合があります。
参考文献
- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド(2023)」/https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
- 日本睡眠学会 一般向け情報(睡眠衛生・概日リズム)/https://jssr.jp/public/
- NHS UK “How to get to sleep”/https://www.nhs.uk/every-mind-matters/mental-wellbeing-tips/how-to-fall-asleep-faster-and-sleep-better/
- CDC “Sleep and Sleep Disorders”(睡眠衛生の基本)/https://www.cdc.gov/sleep/index.html