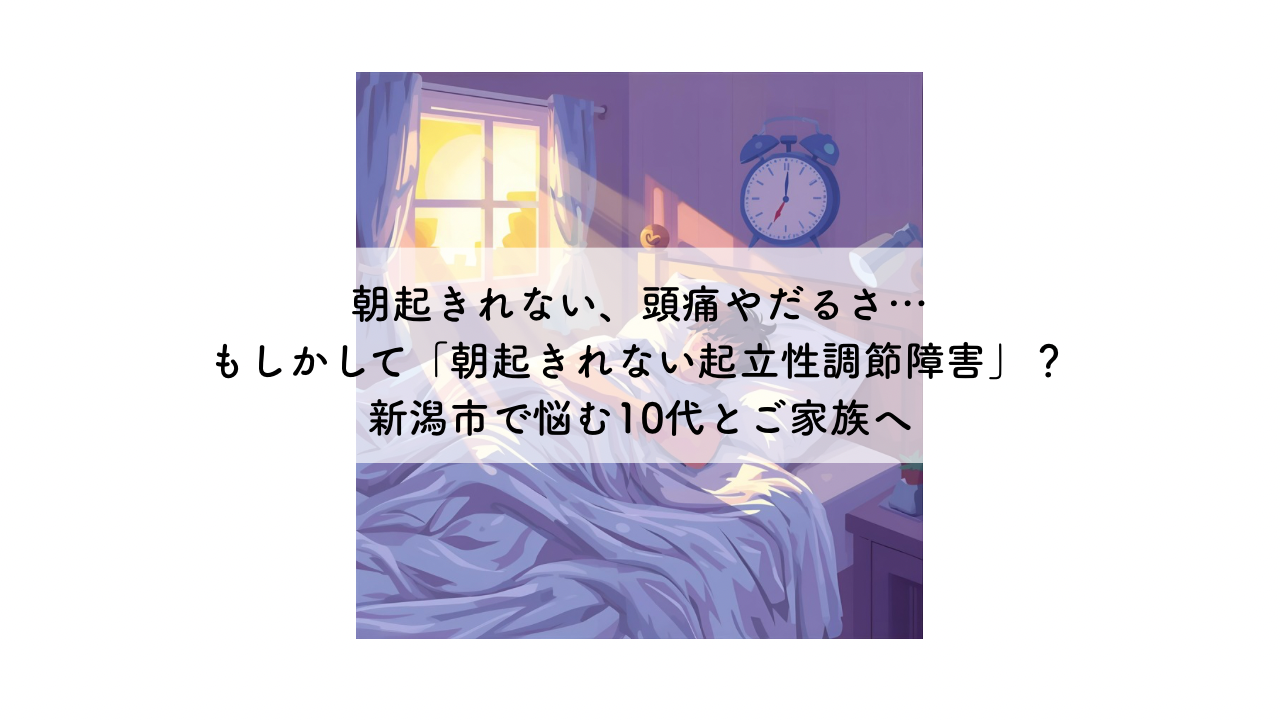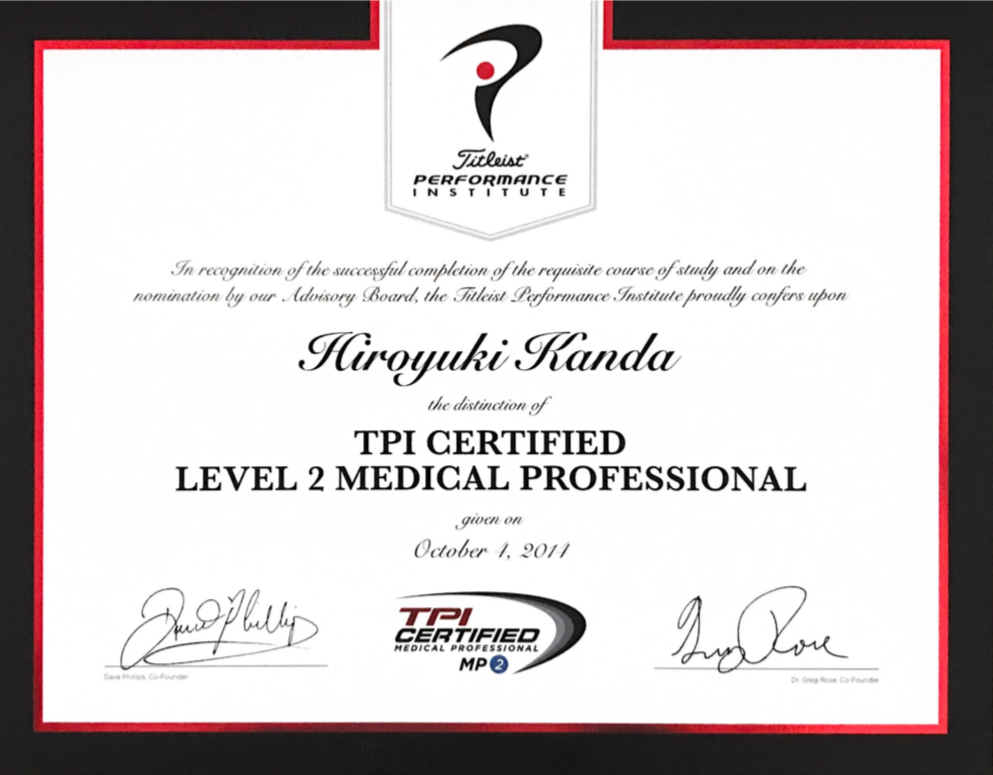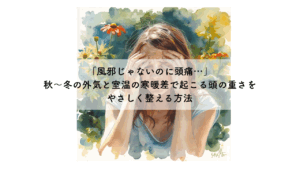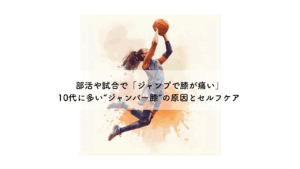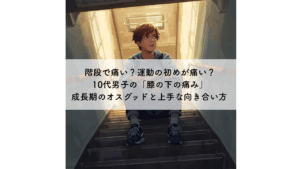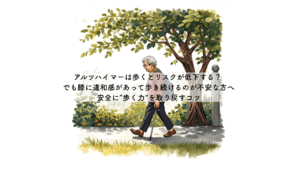こんにちは。新潟市中央区弁天橋通のかんだ整骨院、院長の神田です。
「朝、起こしても起きられない」「頭痛や気持ち悪さで学校へ行けないのに、夕方からは普通に元気そうに見える」。このような様子に戸惑い、「甘えなのでは?」「夜更かしのせい?」と悩まれていませんか。
最近、「朝起きれない起立性調節障害」という言葉を耳にする機会が増えました。ただ、名前だけ一人歩きしてしまい、正しく理解されないまま、お子さん自身もご家族も追い詰められてしまうことが少なくありません。
10代の時期は、勉強・部活・人間関係など、ただでさえストレスが多く、生活リズムも乱れやすい年代です。その中で、朝になると強いだるさ、頭痛、立ちくらみ、動悸などが出て、夕方からやっと体が動きやすくなる状態が続くと、「怠けているのではなく、体の問題かもしれない」と考えてあげることも、とても大切だと感じています。
このページでは、医療機関での診断が必要な「起立性調節障害」という病名をこちらで決めつけることはせず、「朝起きられない」「午前中に体がつらい」という状態を、自律神経・血の巡り・姿勢・体の使い方の面からわかりやすく整理します。
お子さんにもご家族にも、「まずは責めないでいいんだ」と思っていただけるようにお伝えします。
原因とメカニズム
(「朝起きれない起立性調節障害」と呼ばれる状態を身体の視点から)
「朝起きれない起立性調節障害」と説明されることがある状態には、いくつかの要因が重なっていると考えられます。
一つは、自律神経のバランスの問題です。寝ている間は体を休ませる「副交感神経」が優位になり、朝起きて活動するときには「交感神経」が働いて血圧を上げ、脳へしっかり血を送ります。この切り替えがうまくいかないと、起き上がったときに脳への血流が十分に届かず、頭痛や立ちくらみ、強いだるさとして感じられることがあります。
もう一つは、姿勢や体の歪み、筋力バランスです。長時間のスマホ・ゲーム、前かがみでの勉強姿勢、運動不足などが続くと、首・背中・骨盤まわりの筋肉が硬くなり、血の巡りが悪くなりやすいです。その状態で朝を迎えると、「寝たのに疲れが抜けない」「起き上がると余計つらい」につながる場合があります。
さらに、精神的なストレスや脳の疲労(脳ストレス)も影響すると考えられています。学校生活での対人関係の悩み、成績へのプレッシャー、部活での責任感などが続くと、交感神経が休まらず、夜になっても頭や心が「戦闘モード」のままになり、眠りが浅くなります。その結果、朝になっても体が立ち上がる準備が整わない状態が続くことがあります。
起立性調節障害かどうかの診断は、血圧や脈拍の変化などを含め、小児科・循環器科など医療機関での評価が必要です。当院では病名を決めることは行わず、「自律神経の切り替えがうまくいきにくい体」「姿勢や筋肉バランスの崩れ」「ストレスで力が抜けない状態」がないかを丁寧に確認し、体の負担を減らすサポートを目指します。
放置リスクと誤解の解消
まずお伝えしたいのは、「サボり」「甘え」と決めつけてしまうことが、状態を長引かせる一因になりうる、という点です。
朝起きられない状態が続くと、
・学校に行けないことへの罪悪感
・周りから理解されない不安
・生活リズムの乱れによるさらなる体調不良
などが重なり、心身ともに負担が大きくなっていきます。「気合いを入れれば何とかなる」という言葉だけでは、むしろ追い詰めてしまう場合もあります。
一方で、「起立性調節障害だから何もできない」と決めつけてしまうことも、別の負担になります。大事なのは、「体調に合わせてできることを少しずつ整えていく」視点です。
よくある誤解として、
・「夜元気だから本気でつらくないはず」
・「検査で大きな病気がないなら問題ない」
という考えがありますが、自律神経や血の巡りの乱れ、姿勢の崩れは検査に出にくいこともあります。だからこそ、生活習慣、体の使い方、ストレスとの付き合い方を含めて、少しずつ整えていくことが大切と考えられます。
症状が続く場合や、急な体重減少、強い胸痛・動悸・失神などを伴う場合は、必ず医療機関を受診してください。当院は医療機関での診断や治療を否定するものではなく、そのサポート役として関わります。
自分でできる対処法
ここでは、ご家庭で試しやすく、体への負担を減らすための3つの工夫をご紹介します。無理のない範囲で、できるところからで大丈夫です。
1. 「起きる前の30〜60秒」をつくる起床ルーティン
- 目的:急な立ち上がりでフラッとするのを防ぎ、交感神経への切り替えを助ける。
- 手順:
- 目覚ましが鳴ったら、すぐに起き上がらず、仰向けのまま大きく3〜5回、鼻から吸って口から吐く。特に吐く息を長めにしていきます。
- そのまま足首を手前・つま先側へゆっくり10回ほど動かし、ふくらはぎを軽く動かします。
- 上半身を少し横向きにして、肘で支えながらゆっくり起き上がり、座った状態で10秒ほど深呼吸してから立ち上がります。
- 注意点:無理に回数を増やさず、「これならできそう」という範囲から。強いめまい・動悸があれば中止して、必ず医師に相談してください。
- 所要時間目安:30〜60秒。
2. 日中に「水分+軽い動き」をこまめに入れる
- 目的:血の巡りを保ち、交感神経・副交感神経の極端な偏りを防ぐ。
- 手順:
- 朝〜昼にかけて、こまめに少量の水分や麦茶などをとる(目安は合計で1日1.2〜1.5L程度。ただし医師から制限がある場合は指示を優先)。
- 座りっぱなしや横になりっぱなしが30〜60分続いたら、その場で立って背伸びをしたり、足踏みを10〜20回行う。
- 太ももやふくらはぎを、ご家族がさする程度の軽い刺激も血の巡りを助けると考えられます。
- 注意点:激しい運動に切り替える必要はありません。フラつきが強いときは横向きで休むなど、安全を最優先にしてください。
- 所要時間目安:1回あたり30秒〜1分を、1日数回。
3. 就寝前の「首・胸まわりゆるめストレッチ」
- 目的:スマホや勉強で固まりやすい首・胸・背中をゆるめ、眠りの質を整えやすくする。
- 手順:
- ベッドや布団に座り、両手を組んで前ならえのように伸ばし、背中を軽く丸めながら5〜10秒キープ。
- 次に、両手を後ろで軽く組み、胸をひらくようにして5〜10秒、呼吸を止めずにキープ。
- 最後に首を前後左右に「気持ちよい範囲」でゆっくり動かし、それぞれ5秒程度。
- 注意点:痛みが出るほど強く伸ばさないこと。息を止めず、眠気を妨げない程度の軽さで行います。
- 所要時間目安:1〜2分。
これらは「治る」「必ず良くなる」と約束するものではありませんが、体にかかる負担を減らし、自律神経や血の巡りが整いやすい環境づくりとして取り入れていただけると考えられます。
よくある質問(FAQ)
Q1. どのくらいの頻度で通えばいいですか?
A1. お体の状態によりますが、最初は週1回前後で様子をみながら、徐々に間隔をあけていくケースが多いです。無理な来院ペースをおすすめすることはありません。
Q2. どんな人に向いていますか?
A2. 朝の寝起きがつらい、頭痛や立ちくらみが気になる、姿勢の崩れや体のこわばりも気になる、といった10代ご本人や、そのご家族のサポートを求めている方に向いていると考えています。医療機関での治療と並行して、体の使い方や緊張をやわらげたい方にも通っていただくことがあります。
Q3. 神経の反射を使った施術とは痛くないですか?
A3. 当院の施術は、神経の反射を利用したやさしい刺激で、体が自分で力を抜きやすくなることを目指す方法です。いわゆる「ボキボキ鳴らす矯正」や、その場だけ強くもみほぐす施術は行いません。刺激量も年齢や体調に合わせて調整します。
Q4. 医師の診断がなくても行ってよいですか?
A4. 気になる症状がある場合、まずは小児科など医療機関でご相談いただくことをおすすめします。そのうえで、体調管理や姿勢・筋バランスのケアとして当院を利用される方も多くいらっしゃいます。受診の目安も来院時に一緒に確認いたします。
まとめ

- 朝起きられない、午前中の頭痛やだるさ、夕方から元気になる状態は、「怠け」と決めつける前に、自律神経や血の巡り、姿勢・体の緊張を見直したいサインとも考えられます。
- 起立性調節障害かどうかの判断は医療機関で行われますが、日々の生活習慣や体のケアで、負担を軽くしていく余地がある場合もあります。
- お子さんとご家族が、一人で抱え込まずに相談できる場所として、やさしく状態を確認しながらサポートしていきます。
「このくらいで相談してもいいのかな」と迷われる段階でも大丈夫です。遠慮なくご相談ください。無理なく続けられる一歩を、一緒に探していきませんか。
【監修:柔道整復師 神田博行】
電話
TEL 025−211−9541
『ホームページを見て!』とお電話ください。
インターネット予約
24時間いつでもご予約が可能です。
※当日ご希望の方は、お電話にてお願いいたします。
クリック後に予約サイトへ移動します。
LINEからのお問い合わせ
LINE公式アカウントから、お友達追加の後に、フルネームとご用命をお知らせください。
キャンセルについて
当院は完全予約制です。お一人おひとりの施術時間を確保するため、ご予約枠は他の方のご予約をお断りして準備しております。
そのため、直前・当日のキャンセルや無断キャンセルについては、下記のとおりキャンセル料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。
ご予約の変更・キャンセル方法
ご予約の変更/キャンセルは、分かった時点でお早めにご連絡ください。
- お電話:営業時間内
- 留守電/SMS(またはLINE):営業時間外も可(確認後、当院より折り返しします)
キャンセル料について
- 前日までの変更・キャンセル:キャンセル料はかかりません
- 当日のキャンセル(初診):初診料 9,800円をキャンセル料として頂戴します
- 当日のキャンセル(再診):施術料 7,000円をキャンセル料として頂戴します
- 無断キャンセル:ご予約メニューの料金(初診 9,800円/再診 7,000円)をキャンセル料として頂戴します
※「当日」とは、ご予約日(0:00〜ご予約時刻)を指します。
※体調不良などやむを得ない事情の場合も、まずはご相談ください。
遅刻について
遅れることが分かった時点で、必ずお電話またはメッセージでご連絡ください。
ご予約状況により、施術時間の短縮または別日への変更をご案内する場合があります。
また、ご連絡がなく一定時間が経過した場合は無断キャンセル扱いとなることがあります。
お支払い方法(キャンセル料)
キャンセル料は、原則として
- 次回ご来院時にお支払い または
- お振込み等(ご希望に応じてご案内) でお願いしております。
ポリシーの見直し
予約枠の確保とサービス維持のため、内容は予告なく変更する場合があります。
参考文献
- 日本小児心身医学会編:小児起立性調節障害診療ガイドライン改訂第3版/概要・患者向け資料
- 起立性調節障害(小児科 解説記事)Clinicalsup.jp/https://clinicalsup.jp/
- 国立成育医療研究センター「起立性調節障害について(子ども・保護者向け情報)」
- Mayo Clinic Proceedings: Postural orthostatic tachycardia syndrome in adolescents(英語論文の総説)