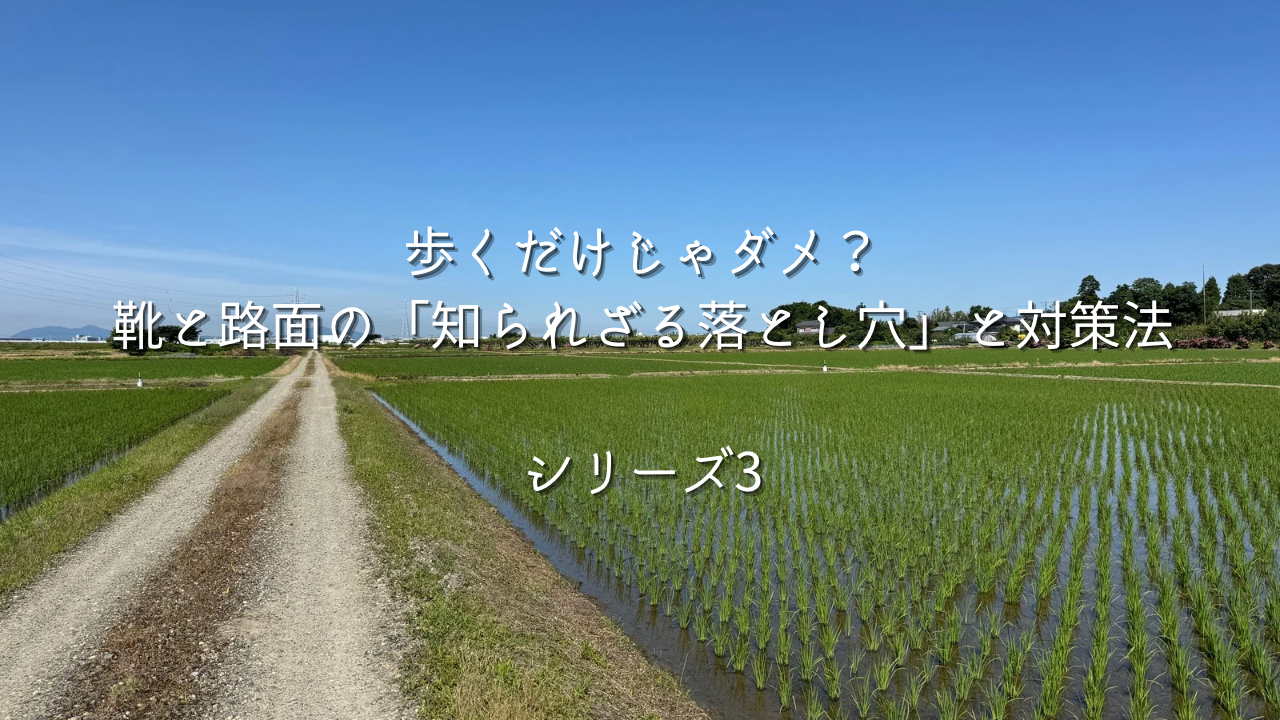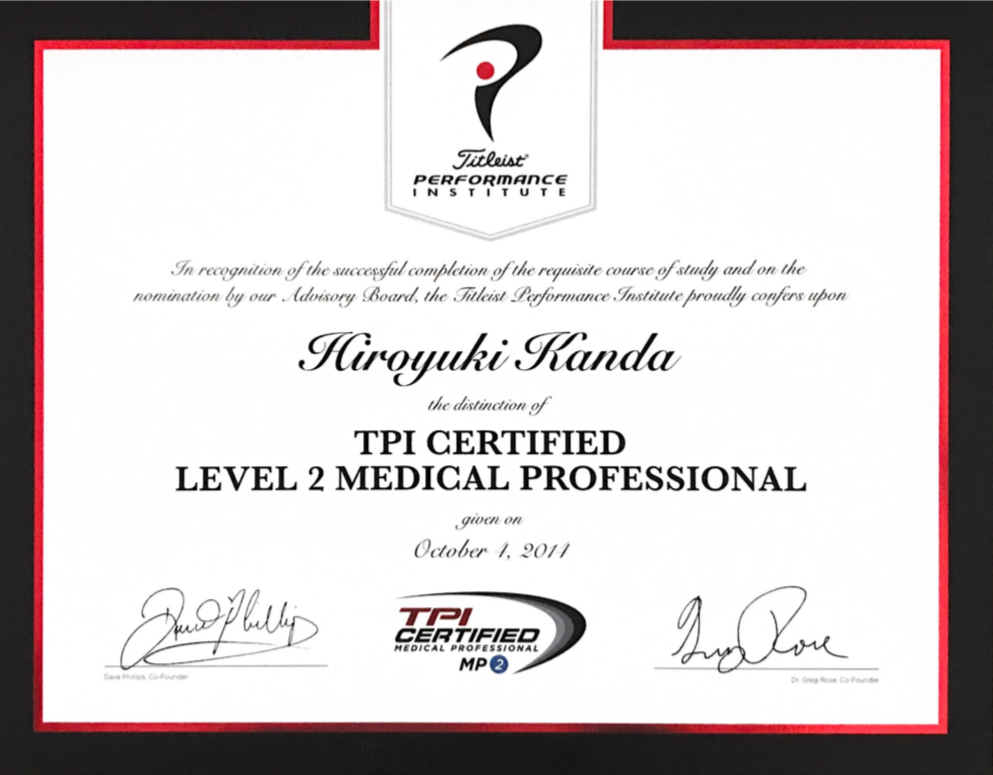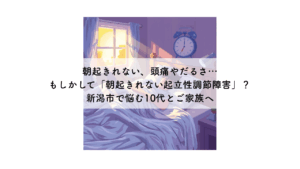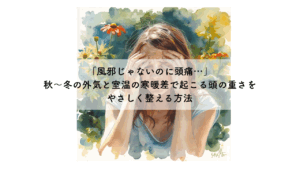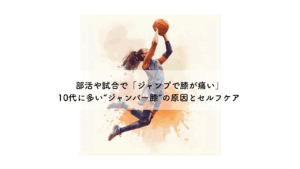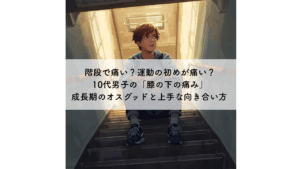こんにちは、新潟市中央区弁天橋通のかんだ整骨院です。
歩くシリーズの2回目は、ウォーキングの効果的な時間・歩数を書かせていただきました。
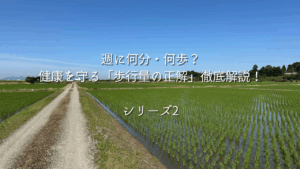
ちなみに1回目は、ウォーキングの効果です。
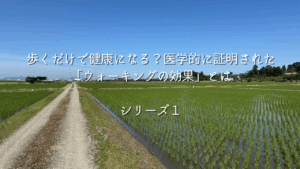
今回、3回目の記事では、最新の研究や臨床経験をもとに、歩行における“靴”と“路面”の重要性について、解説させていただきます。
- 健康のために毎日歩いているのに、なんだか膝や腰が痛い…
- ウォーキングを始めてから、足の裏に違和感が出てきた…
せっかくのウォーキングが、悲しいですよね。
実は、このようなネガティブな結果は、歩く内容そのものよりも、歩く“足元の環境”が原因になっていることが少なくありません。
普段意識していない「路面の硬さ」や「靴のクッション性」が、身体に思わぬ負担をかけていることがあるのです。
ウォーキング後に体の違和感が出てしまう方は、ひょっとして当てはまるかもしれません、
路面によって変わる「歩くときの負担」—あなたの足元は大丈夫?

歩くことが健康に良いのは間違いありませんが、“どこを歩くか”によって、体への負担が大きく変わることをご存じでしょうか?
日常で当たり前に歩いている場所にも、実はメリット・デメリットがあるのです。ここでは、代表的な路面の特徴と注意点をわかりやすく解説します。
アスファルトやコンクリートの道を歩くときは…
私たちがふだん最も多く歩いているのが、アスファルトやコンクリートで舗装された道です。
通勤・通学・買い物など、どこへ行くにも便利な一方で、地面の硬さが非常に高いという特徴があります。
この硬い地面を歩くと、足の裏で受けた衝撃が吸収されず、そのまま足首→膝→腰→背骨へと伝わってしまうため、身体に負担がかかりやすくなります。
とくに、以下のような方は注意が必要です:
- クッション性の少ない靴を履いている方
- 膝や股関節、腰などに痛みがある方
- 体重が重めの方、または加齢によって筋力が低下している方
このような状態でアスファルトの上を長時間歩き続けると、足腰の疲労の蓄積はもちろん、関節の炎症や軟骨の摩耗といったトラブルにつながる恐れもあります。
芝生や土の道、トレッドミルなど「やわらかい地面」のメリット、デメリット

一方で、公園の芝生や土の道など、地面にある程度の“やわらかさ”がある場所では、歩行時の衝撃を吸収しやすくなります。
このような路面には「着地時の衝撃が少ないため、足や膝に優しい」メリットがあります。
特に膝や腰に負担がかかりやすい方、運動習慣をこれから始めたい方には、こうした柔らかめの地面がおすすめです。
さりとて、お住まいの地域によっては、なかなかこのような「体に負担の少ない環境で歩く場所がない」といったこともよく耳にします。
また、スポーツジムに設置されている地面が動く『トレッドミル』も、衝撃が少なくなるような設計で負担が少ないです。
ですが、自動で足元が動くため、ご高齢な方や足腰に不安がある方には、転倒や体の故障につながるリスクが高まるのも事実です。
砂浜や山道は「運動効果は高い」が初心者にはやや難易度高め
海辺の砂浜や自然の山道など、舗装されていない道(不整地)を歩くことは、筋力やバランス力を高める上でとても良い運動になります。
地面の不安定さが、足や体幹の筋肉をより使わせてくれるため、運動効果が高いのは間違いありません。
しかしその分、身体への要求も高くなるため、以下のようなリスクにも注意が必要です:
- 足首をひねる(捻挫)リスク
- 足の裏の筋膜に負担がかかりやすく、足底筋膜炎の原因に
- 地面の不整による膝・腰へのねじれストレス
こうした道は体力や筋力がついてから、または十分な準備をした上で取り入れるのが安心です。
とくに、運動初心者の方やリハビリ中の方には、なるべく平坦でやわらかめの地面を歩くことをおすすめします。
「歩くこと」は、簡単に始められる健康法ですが、足元の環境によって、その効果やリスクは大きく変わるということをぜひ覚えておいてください。
ご自身の体調や体力に合った“歩く場所”を選ぶことで、無理なく、安心して健康習慣を続けていけるはずです。
「理想の靴」とは?クッション性が高すぎる靴にご注意を

ウォーキングシューズを選ぶとき、「クッション性が高いほど足に良さそう」と思っていませんか?
最近では「高反発」「厚底」「スーパークッション」など、足を守ることをうたった靴が多く販売されています。たしかに、衝撃を吸収してくれるという点では心強いのですが、実はクッション性が高すぎる靴には、思わぬ落とし穴があるのです。
クッションが厚すぎると「足裏の感覚」が鈍くなる
人間の足の裏には、身体のバランスを保つための“センサー”がたくさんあります。髪の毛一本でも、足の裏で踏んでしまうと違和感を感じたことがある経験はありませんか?それくらい感覚が鋭い部位です。
ところが、靴底が柔らかすぎると、その地面の感覚が足裏に伝わりにくくなり、姿勢を調整したり、バランスをとる能力が低下してしまう可能性があります。
特に高齢者の場合は、
- 転倒リスクの上昇
- 膝や股関節の位置感覚の鈍化
といった影響が報告されており、注意が必要です。
足の筋肉を「使わなくなる」ことによる弊害も
柔らかい靴底は、一見歩きやすそうに見えますが、長期間それに頼りすぎると、足本来の機能が弱くなる恐れもあります。
具体的には、
- 衝撃を吸収する力(足のアーチのバネ)
- 指先を使って踏み込む動作
などがうまく働かなくなり、次のような症状につながることも:
- 足底筋膜炎(かかとの痛み)
- 外反母趾(親指の変形)
- 扁平足(アーチの低下)
つまり、守りすぎる靴は、逆に足の力を奪ってしまうこともあるのです。
理想的なウォーキングシューズの選び方
では、どんな靴を選べば良いのでしょうか?
大切なのは、“適度なクッション性”と“足に合った構造”です。
✔ 靴選びで意識したい3つのポイント
・かかとがしっかりと安定していること(ヒールカウンターが硬め)

ヒールカウンターとは、靴のかかと部分に内蔵されているかかとを支える芯材(補強パーツ)のことです。
かかとの形を保ち、足が靴の中でグラつかないように安定させる役割を担っています。
🔹 ヒールカウンターは何がいいの?
足全体のバランスをサポート → 正しい歩行姿勢を保ちやすくなります。靴選びで一番重要と言っても過言ではないのが、ヒールカウンターがしっかりしていることです。
靴の脱いだり履いたりする際に、踵を潰してしまうことがあるかもしれません。それは、靴の性能を落としてしまうばかりか、足元の不安定につながりますので、注意が必要です。
- 足首やかかとの安定性が増す → 歩行中に足が内側や外側に倒れにくくなります。
- 靴のフィット感が良くなる → かかとが脱げにくくなり、無駄な動きが減るため疲れにくくなります。
さらに、
- 自分の足型に合っているか(幅広・甲高など)
- つま先に1cm程度のゆとりがあるか(足はだんだん浮腫んできます。足のサイズも変化しますので、午後に選んだ方がいい場合もあります)
といった点にも気を配りましょう。
可能であれば、靴専門店で足のサイズ測定や歩行チェックを受けてから選ぶのが理想的です。
まとめ:正しく歩けば、もっと健康になれる!

歩くこと自体は、身体にとって素晴らしい健康習慣です。ですが「どこを、どんな靴で、どう歩くか」によって、その効果は大きく変わってきます。
今回の記事を参考にしていただき、ウォーキングの参考にしていただけたら幸いです。
また、『靴が合わなくて足が痛い』『歪んだ靴を長く履いていたせいで、体のバランスがおかしいかも?』とお困りの方は、当院の治療がお役に立てると思います。遠慮なくご相談くださいませ。
🦶3部作のまとめ
歩行ブログ3部作、いかがでしたでしょうか?
- 第1回:歩行の驚くべき健康効果
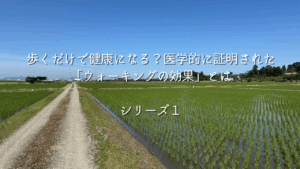
- 第2回:目的別・最適な歩行時間や歩数
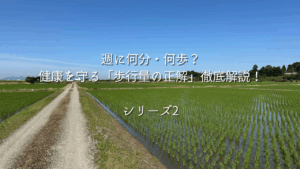
- 第3回:足元の環境とシューズ選びの大切さ
このシリーズが、「今日からの歩き方」を見直すきっかけになれば幸いです。
今後も、皆さまの健康と快適な生活をサポートする情報を発信してまいります。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
【監修:柔道整復師 神田博行】
電話
TEL 025−211−9541
『ホームページを見て!』とお電話ください。
インターネット予約
24時間いつでもご予約が可能です。
※当日ご希望の方は、お電話にてお願いいたします。
クリック後に予約サイトへ移動します。
LINEからのお問い合わせ
LINE公式アカウントから、お友達追加の後に、フルネームとご用命をお知らせください。
キャンセルについて
当院は完全予約制です。お一人おひとりの施術時間を確保するため、ご予約枠は他の方のご予約をお断りして準備しております。
そのため、直前・当日のキャンセルや無断キャンセルについては、下記のとおりキャンセル料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。
ご予約の変更・キャンセル方法
ご予約の変更/キャンセルは、分かった時点でお早めにご連絡ください。
- お電話:営業時間内
- 留守電/SMS(またはLINE):営業時間外も可(確認後、当院より折り返しします)
キャンセル料について
- 前日までの変更・キャンセル:キャンセル料はかかりません
- 当日のキャンセル(初診):初診料 9,800円をキャンセル料として頂戴します
- 当日のキャンセル(再診):施術料 7,000円をキャンセル料として頂戴します
- 無断キャンセル:ご予約メニューの料金(初診 9,800円/再診 7,000円)をキャンセル料として頂戴します
※「当日」とは、ご予約日(0:00〜ご予約時刻)を指します。
※体調不良などやむを得ない事情の場合も、まずはご相談ください。
遅刻について
遅れることが分かった時点で、必ずお電話またはメッセージでご連絡ください。
ご予約状況により、施術時間の短縮または別日への変更をご案内する場合があります。
また、ご連絡がなく一定時間が経過した場合は無断キャンセル扱いとなることがあります。
お支払い方法(キャンセル料)
キャンセル料は、原則として
- 次回ご来院時にお支払い または
- お振込み等(ご希望に応じてご案内) でお願いしております。
ポリシーの見直し
予約枠の確保とサービス維持のため、内容は予告なく変更する場合があります。