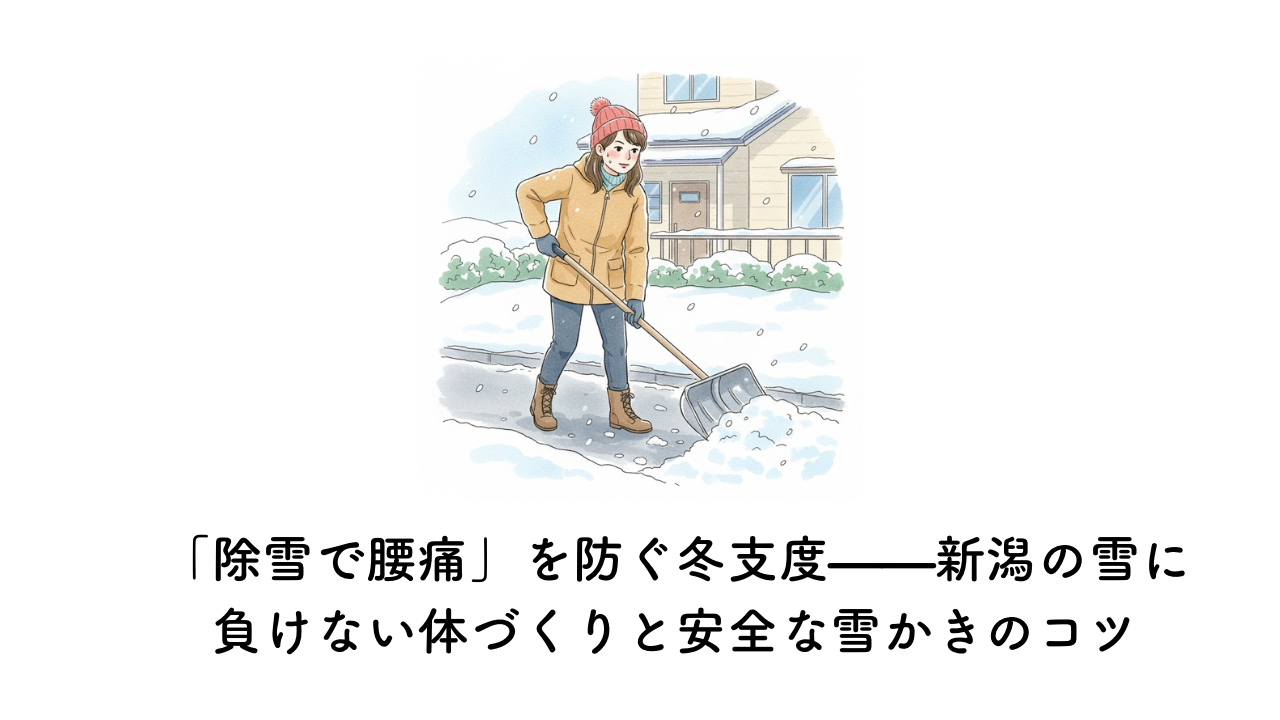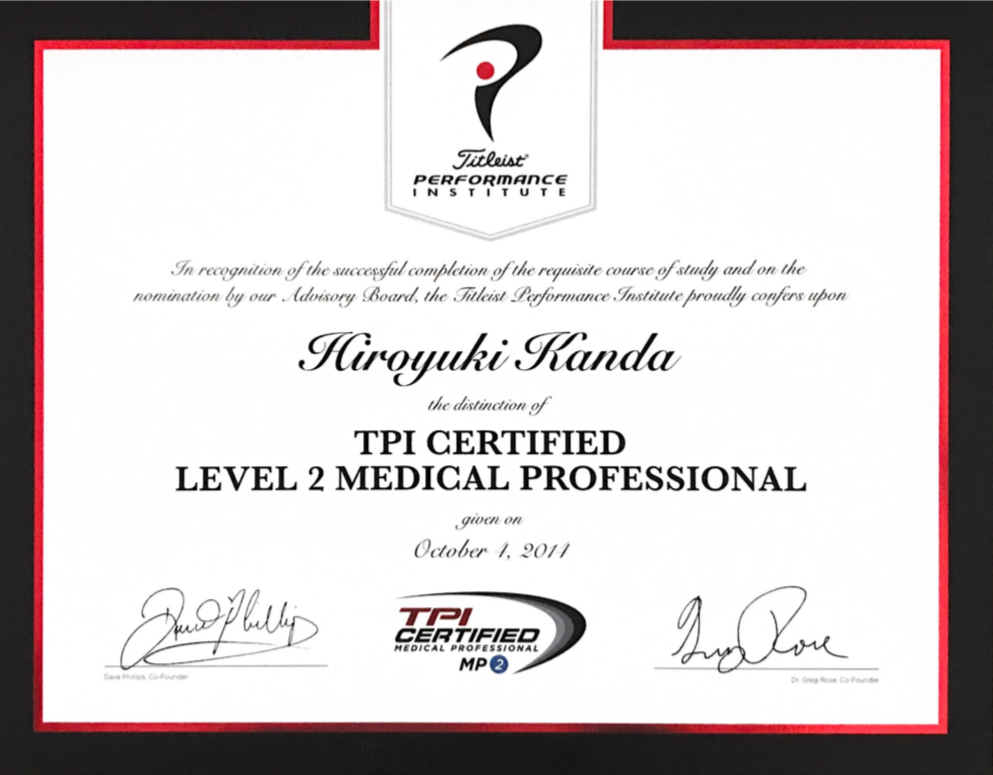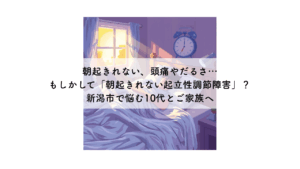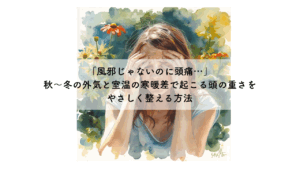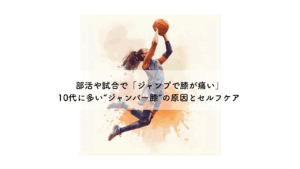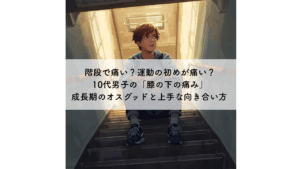こんにちは。新潟市中央区弁天橋通のかんだ整骨院、神田です。
「除雪の腰痛に備える」——冬の訪れとともに、毎年多くいただくご相談です。
朝いちばん、玄関先の重たい雪を持ち上げた瞬間に「グキッ」と来た、途中から腰が固まって動けなくなった…こうしたお声は少なくありません。
今日は、**「除雪で腰痛」**が起きやすい理由と、今日からできる備え・安全な作業フォームをわかりやすくまとめます。
2) 原因とメカニズム——なぜ「除雪で腰痛」が起きやすいのか
1. 腰に負担が集中しやすい作業条件
雪は水分を含むほど重くなり、持ち上げ・前屈・ねじりが同時に起きやすい作業です。前かがみ+ひねりは腰部の負担を増やす代表的な組み合わせで、対象物(雪)を体から離して持つほど負担は増します。厚生労働省の指針でも、前屈や中腰・ひねりを避け、作業対象にできるだけ体を近づけることが示されています。
2. 寒さと自律神経(交感神経)
寒冷にさらされると、体は熱を逃がさないため交感神経が高まり、血管が収縮して筋がこわばりやすくなります。屋内外の温度差が大きい朝ほど反応は強く、準備不足のまま重作業を始めると腰部の筋・靭帯にストレスがかかりやすくなります。
3. 姿勢・体の歪み・積み重なる疲労
雪かきは反復作業です。姿勢の崩れ(体の歪み)や左右偏りが続くと、腰だけでなく殿部・太もも・背中にも硬さが波及して「翌日以降に痛む」「積雪が増えるほど辛い」という悪循環になります。ガイドラインでも、危険信号がなければ過度な安静より、姿勢・動作を整えながら活動を維持する管理が推奨されています。
放置リスクと誤解の解消
- 放置リスク:かばい姿勢がクセになり、姿勢の崩れが固定化 → 別部位(背中・股関節・膝)への負担増。必要に応じて評価・計画的な運動へつなぐことが大切です。
- 誤解①「骨盤を一度で“リセット”すればOK」 → 骨盤・背骨は日々の動作で常に変化します。単発の矯正で恒久的に固定されるわけではなく、姿勢・フォームの習慣を併せて整えることが現実的です。
- 誤解②「痛い日は完全安静が一番」 → 危険信号がなければ、動ける範囲で活動を保つ方が回復に有利とされます。無理は禁物ですが、適切な負荷・ストレッチ・休息の組み合わせが重要です。
- 安全面の注意:屋根の雪下ろし・除雪機使用は転落・巻き込まれ等のリスクが高い作業です。2人以上で、命綱や安全装置の徹底など自治体の注意事項に従いましょう。
自分でできる対処法(道具いらず・今日から3つ)
※強い痛み・しびれが増す場合は中止し、評価を受けてください。
① 作業前3分のあたため&可動化
- 目的:温度差で高ぶった交感神経と筋のこわばりを落とし、腰まわりに準備をつくる。
- 手順:
- 室内で鼻から3秒吸って口から6秒吐く×5呼吸(肩の力を抜く)。
- いす座位で殿部ストレッチ:片足を反対膝にのせ、背すじを伸ばして20〜30秒×左右。
- 立位でふくらはぎ・もも前を壁押しで各20秒×2。
- 注意点:反動はつけない。冷え込む日は上着・首元の保温を先に。
- 所要時間の目安:約3分。 (寒冷時の血管収縮・交感神経立進への配慮、入浴や睡眠ガイドでも温熱・環境の整えが推奨されています。)
② 腰にやさしい「押して運ぶ・ひねらない」フォーム
- 目的:前屈・ひねりを減らし、荷重を分散して姿勢を保つ。
- 手順:
- スコップは体に近く。膝を軽く曲げ、股関節から折る(ヒップヒンジ)。
- 持ち上げる量は少なめにして、前へ押す/引きずらずに運ぶ。
- 方向転換は腰だけひねらず、足ごと向き直る。
- 注意点:長時間の同一姿勢は避け、10〜15分ごとに小休止。できれば左右の手・足さばきを入れ替える。
- 所要時間の目安:作業中ずっと意識。 (厚労省指針は「中腰・ひねりを避け、対象に近づく」「同一姿勢を長時間続けない」を推奨しています。)
③ 作業後10分の「ほどきケア」
- 目的:反復作業で固まった腰・殿部・太ももをやさしく解き、翌日の張りを軽くする。
- 手順:
- うつむき深呼吸5回→背中を丸め・反らし各5回(痛みがなければ)。
- 殿部ストレッチ20〜30秒×2/ふくらはぎ・もも前20〜30秒×2。
- ぬるめの入浴またはカイロで腰・殿部を軽く保温。
- 注意点:鋭い痛み・しびれが強まる姿勢は避ける。入浴は熱すぎに注意。
- 所要時間の目安:10〜15分。 (「急激な温度変化」は自律神経負担になります。保温しつつクールダウンを。)
時間帯別のヒント
・朝:作業前3分の準備+軽い朝食・水分。
・日中:10〜15分ごとに小休止、こまめに押して運ぶへ切替。
・就寝前:短時間のストレッチと深呼吸で翌日に疲れを残さない。
よくある質問(FAQ)
Q1. 費用の目安は?
A. 当院は自費施術です。初回9,800円/2回目以降7,000円が目安です(評価内容により前後)。まずは相談だけでも大丈夫です。
Q2. 通院頻度は?
A. 初期は週1回前後で症状と動作の改善を確認し、その後は隔週〜月1回で再発予防のメンテナンスをご提案します。
Q3. どんな人に向きますか?
A. 「強い刺激が苦手」「姿勢や体の歪みを整えたい」「自分でも続けられるストレッチを覚えたい」方に。神経の反射を活用したやさしい施術で、冬場の除雪負担に耐える体づくりを一緒に進めます。
Q4. 医療機関を急ぐサインは?
A. 発熱、夜間も強い痛み、足の脱力・しびれの急な悪化、排尿・排便の障害、転倒・けが直後の痛み等は早めに整形外科で評価を。腰痛ガイドラインが示すレッドフラッグに相当します。
まとめ
- 除雪で腰痛は、前屈+ひねり+重さ+寒さが重なることで起きやすくなります。まずは対象を体に近づけ、ひねらず足で向きを変える。
- 作業前後の3分準備/10分ほどき、作業中の小休止と左右交替で、筋のこわばりと疲労の偏りを防ぎましょう。
- 安全面(屋根・除雪機)は2人以上・安全装置・命綱など自治体の注意事項に従って無理をしないこと。 寒い季節を、無理なく乗り切る一歩をご一緒します。
お困りの方は 【電話】025-211-9541 または 【LINE公式】https://page.line.me/jeo9591r へ。インターネット予約も承ります:https://base-first.com/reservation/
※「まずは相談だけでもOK」です。お気軽にどうぞ。
参考文献
- 厚生労働省『職場における腰痛予防対策指針(解説含む)』PDF(作業姿勢・同一姿勢回避・対象物を近づける等の原則)https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001376468.pdf
- 日本医療機能評価機構 Minds『腰痛診療ガイドライン2019(改訂第2版)』概要ページ https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00498/
- 新潟県『雪処理事故防止リーフレット』PDF(転落・除雪機事故防止の留意点)https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/429945.pdf
- 済生会『温度差で起こるヒートショックに注意』(温度差と血圧変動への配慮)https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/heatshock/
(本記事は一般的な情報提供です。診断や効果の断定はしておらず、個々の状態に合わせた評価・施術が必要です。)