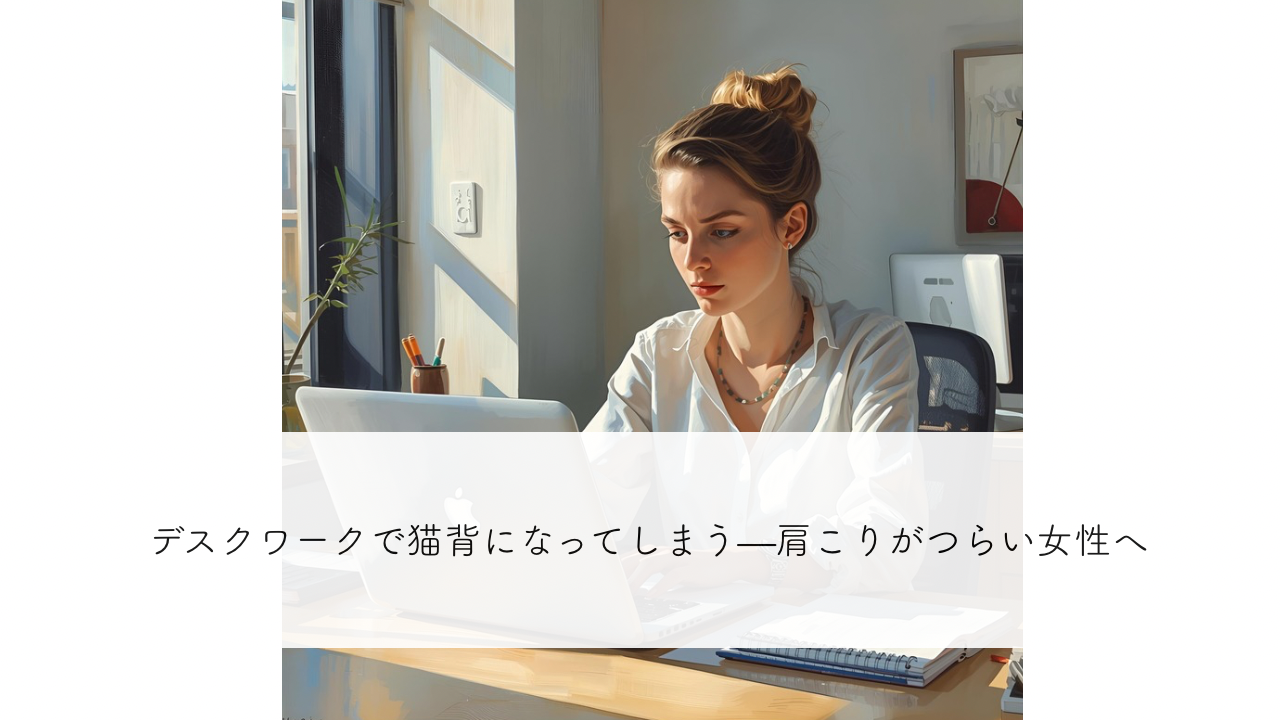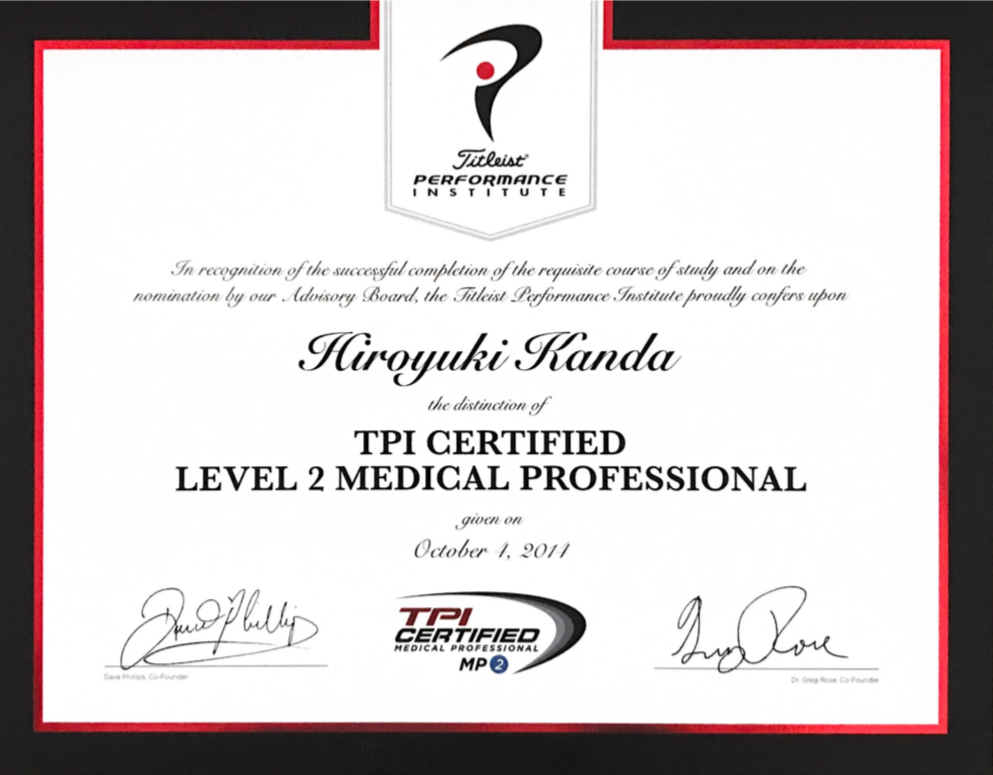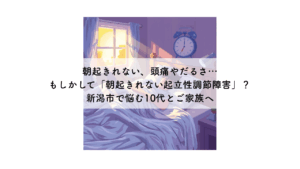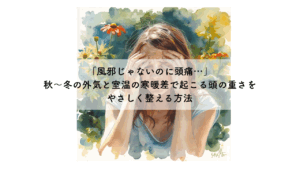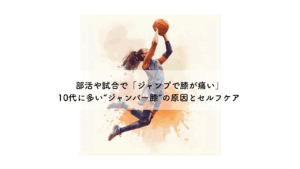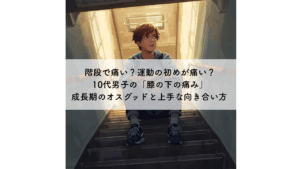こんにちは。新潟市中央区弁天橋通のかんだ整骨院、院長の神田です。
「デスクワークで猫背になってしまうせいか、肩こりが続く…」そんなお困りはありませんか。図面チェックやCAD作業に集中していると、知らないうちに頭が前に出て背中が丸まり、夕方には肩から首すじが重たくなる。建築士など設計・監理の現場では、締切前に長時間の座位が続き、帰宅後もスマホでやり取り…という“あるある”が重なりやすいものです。
本記事では、体の歪みと自律神経(交感神経)という二つの視点から、猫背と肩こりの関係をやさしく整理し、今日からできる現実的な対処をお伝えします。
原因とメカニズム
1) 姿勢—「頭が前に出る」と肩がこる理由
モニターや図面に顔を近づける前かがみ姿勢が続くと、頭の重さ(約4〜6kg)が首の付け根にかかるモーメントを増やします。僧帽筋や肩甲挙筋が張り、肩甲骨は外に滑りやすく、首〜肩まわりの筋に持続的な緊張が生まれます。いわゆる“猫背”は胸郭も硬くなり、呼吸が浅くなりやすいため、筋のこわばりが抜けにくい土台をつくります。ディスプレイ作業では、作業環境(画面位置・明るさ・椅子・机の高さ)と姿勢・休憩の取り方が肩こりに影響します。厚生労働省の「情報機器作業(VDT作業)ガイドライン」でも、適切な作業環境づくりと定期的休止が推奨されています。
2) 自律神経—交感神経優位で“力が抜けない”
緊張や集中が続くと交感神経が優位になり、筋は“戦闘モード”のままになりがちです。呼吸が浅くなると、首・肩の補助呼吸筋に負担が移り、こわばりが持続します。長く座り続けることで血流が滞りやすくなる点も、肩こりを感じやすくする一因です。座位時間を減らし、短い活動をこまめに挟むことは健康面でも有利とされ、国内機関が翻訳したWHOガイドラインでも「座り過ぎを減らす」「できる活動を少しずつ増やす」ことが勧められています。
3) デスクワーク特有の負荷—建築士の“見落としがちな三点”
設計・積算・申請業務などは長時間の画面注視になりやすく、(1)モニターの高さが低い/二枚目のサブモニターが斜め過ぎる、(2)椅子の座面が高すぎて足が床に安定しない、(3)ノートPC単体で前傾を強いる、などの環境要因が積み重なります。英国NHSの実践ガイドでも「椅子・机・画面の高さ調整」「骨盤を立てる座り方」「こまめなポジション変更」が推奨されています。
放置リスクと誤解の解消
肩こりは生命に直結しない不調に見えますが、放置すると頭痛や集中力低下、睡眠の質の低下につながることがあります。一方で「骨盤や背骨は一度で“リセット”できる」といった期待は現実的ではありません。
姿勢は“環境×習慣×体の反応”の結果です。作業環境の見直し、短時間の動きの挿入、呼吸の整え方などを組み合わせ、少しずつ「戻りにくい」体の使い方へ育てていくことが、遠回りなようで近道です。
自分でできる対処法
- 〔モニターと椅子の三点合わせ—“目線・肘・足裏”をそろえる〕 目的: 首肩の過緊張を減らし、猫背に戻りにくい座位を作る。 手順: 1) 画面上端が目線の少し下(2–3cm程度)にくる高さへ。2) 肘は90度前後で机に軽く触れる。3) 足裏は床にベタ置き、かかとが自然に収まる位置へ(合わなければフットレスト代用で雑誌など)。 注意点: ノートPC単体は前傾を招きやすいので、可能なら外付けキーボード+台で高さを補正。明るさ・コントラストも過不足のない設定に。 所要時間目安: 初期調整10分+微調整1–2分/日。 (作業環境と休止の考え方はVDTガイドラインでも示されています。)
- 〔“60分に1回、60秒”のリセット—胸を開き、呼吸を深く〕 目的: 交感神経優位をゆるめ、肩甲帯の血流を促す。 手順: 1) 60分作業したら立ち上がり、胸の前で両手を広げて肩甲骨を寄せる。2) 鼻から4秒吸って、口から6秒で吐く呼吸を5〜6サイクル。3) 目線を遠くに置いて視野を広げる。 注意点: 痛みが強い日は無理をしない。めまい・しびれなどがあれば中止し、必要に応じて医療機関へ。 所要時間目安: 60〜90秒/回を1日数回。 (長時間座位の軽減と“こまめな活動”は国際ガイドラインでも推奨。)
- 〔就寝前の“背中ほぐし”—床でできる胸椎の伸展〕 目的: 一日の前かがみ姿勢で硬くなった胸まわりをやさしく戻す。 手順: 1) バスタオルをゆるく丸め、肩甲骨の少し下に横向きに置く。2) 仰向けでゆっくり寝て、腕を大きく広げ、呼吸を深く。3) ほどよい心地よさで1〜2分。 注意点: 強い痛みや既往(骨粗しょう症など)がある場合は避ける。反り腰が強い方は丸めタオルを小さめに。 所要時間目安: 1〜2分/就寝前。 (姿勢変換と自分に合った範囲での実践が大切。NHSの姿勢実践リーフでも“無理のない調整”が勧められています。)
よくある質問(FAQ)
Q1. どれくらいの頻度で通えばよいですか?
A1. 症状や生活環境で異なりますが、はじめは週1回前後で姿勢・呼吸・動作の“型”を身につけ、その後は間隔をあけていく流れが一般的です。変化の出方には個人差があります。
Q2. 料金はどのくらいですか?
A2. 当院は自費の整骨院です。初回はカウンセリング・検査を含めて9,800円、2回目以降は7,000円です(保険適用外)。過度な矯正や強揉みは行わず、神経の反射を活用したやさしい施術を中心に進めます。
Q3. どんな人に向いていますか?
A3. デスクワークや図面作業で猫背になりやすい方、肩こりと同時に呼吸の浅さ・集中のしにくさを感じる方、“一度で劇的に”ではなく、環境と習慣から整えたい方に向いていると考えます。
Q4. 仕事が繁忙で席を離れにくいのですが…
A4. 完全な休憩が難しい日でも、画面と目線の距離を一時的に離す、座面で坐骨を立て直す、深呼吸を3回だけ行う等の“超ミニリセット”は可能です。積み重ねが姿勢の戻りを防ぎます。VDT作業でも“こまめな休止”は推奨されています。
まとめ
- デスクワークで猫背になってしまうと、首・肩の筋緊張と呼吸の浅さが重なり、肩こりを自覚しやすくなります。
- 作業環境の調整(画面・椅子・足裏)と“こまめな姿勢変換”が、肩こりの土台づくりに有効と考えられます。
- 無理のない範囲でできることから始め、習慣化を目指すことが遠回りに見えて近道です。
【監修:柔道整復師 神田博行】
参考文献
- 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(VDT)」—作業環境・休止の考え方。
- WHO身体活動ガイドライン(国立健康・栄養研究所訳)—座位時間の低減とこまめな活動の推奨。
- Buckinghamshire Healthcare NHS Trust “Setting up your workstation” —椅子・机・画面の調整、こまめな姿勢変更。