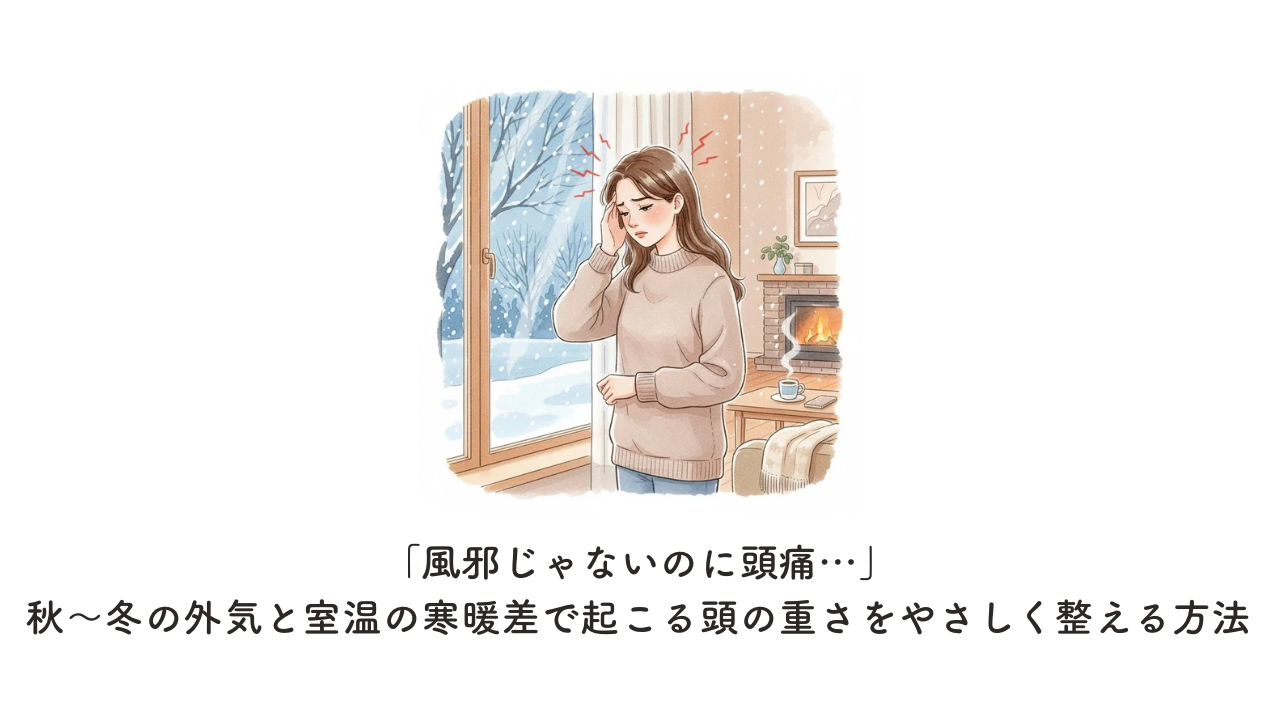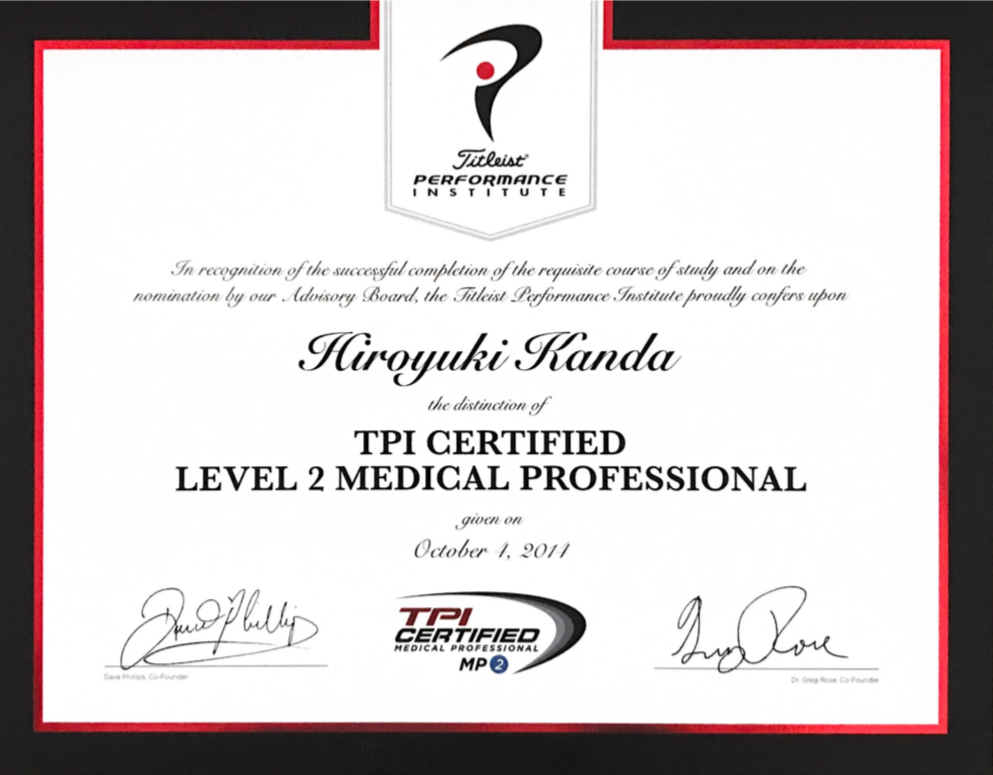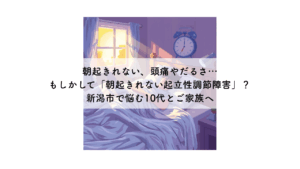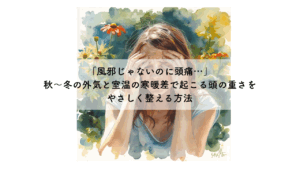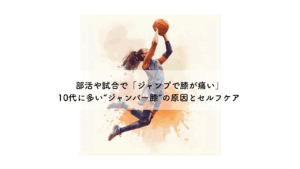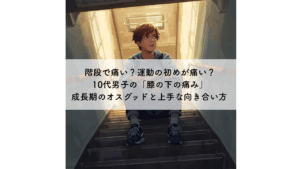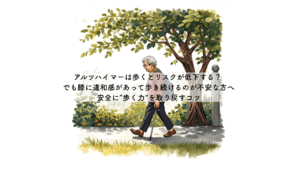こんにちは。新潟市中央区弁天橋通のかんだ整骨院、神田です。「風邪をひいていないのに頭痛が続く」ことでお困りではありませんか?
秋から冬へ向かう時期は、外の冷たい空気と暖房の効いた室内との外気と室温の寒暖差が大きくなります。出勤時はひんやり、オフィスは暖かい、夕方の買い物でまた冷える
——この温度差のくり返しが自律神経に負担をかけ、首肩の筋緊張や血管の反応性を高めて頭の重さや痛みにつながることがあります。
特に20〜60代の女性では、家事やデスクワークで前かがみになりやすく、姿勢の崩れや体の歪みが重なると「夕方にズキズキ」「朝から重だるい」といった訴えが増えます。
本記事では、寒暖差にまつわる頭痛の仕組みと、今日からできるやさしい整え方をご紹介します。
原因とメカニズム
1. 「外気と室温の寒暖差」と自律神経の関係
寒い所では血管が収縮し、温かい所では拡張します。この切り替えを担うのが自律神経(交感神経/副交感神経)で、気温や気圧・湿度などの気象変化は頭痛を誘発・増悪し得ることが報告されています。日本頭痛学会の解説でも天候と頭痛の密接な関係が示され、環境変化が症状と関連する科学的報告が紹介されています。
頭痛の代表である片頭痛や緊張型頭痛は、誘発因子(トリガー)として環境要因やストレス、睡眠・生活リズムの乱れが関与しうるとされます。
2. 「脳疲労」と首肩のこわばり
温度差により交感神経が優位な時間が長くなると、呼吸は浅く、首肩の筋はこわばりがち。結果として緊張型頭痛の特徴である締め付け感・重だるさが出やすくなります。生活要因の調整(同じ姿勢を避ける、温める、体操など)が基本とされています。
3. 片頭痛タイプへの波及
温度差・気圧変化・湿度などの気象要因は、片頭痛の誘発因子としても議論され、医療系解説や学会資料で取り上げられています(気象の変化で受診が増える・症状が悪化するとの報告など)。
※片頭痛はズキズキする拍動性、光・音過敏、吐き気などを伴いやすいタイプです。
放置リスクとよくある誤解
- 放置リスク:痛み→安静しすぎ→さらに血流低下・筋硬直→痛み増悪…という悪循環に入りやすく、痛みに注意が向きやすい「脳の疲れ(脳疲労)」も強まりがちです。生活の小さな調整を積み重ねることが、長い目でみて有利です。
- 誤解1「強く揉めば早く治る」:過度な刺激は防御反応で余計にこわばることがあります。やさしい動き・温め・呼吸のセットが安全です。
- 誤解2「寒暖差はどうにもならない」:室温・衣服・行動の工夫で温度差の当たり方は減らせます(室温や服装の調整など、生活リズムの整備は一次性頭痛の対策として推奨されます)。
- 誤解3「歪みを一度で“リセット”すればOK」:からだは連動して動きます。首・肩・胸郭・骨盤の協調を少しずつ整える視点が大切です。
※次のレッドフラッグがあれば、速やかに医療機関(頭痛外来・脳神経内科等)へ:突然の激しい頭痛、神経症状(しびれ・麻痺・ろれつ困難・視野異常)、発熱や項部硬直、外傷後、50歳以降の新規頭痛など。診療ガイドラインでもSNNOOP10として注意喚起されています。
自分でできる対処法
以下は目的→手順(1,2,3)→注意点→所要時間の順でまとめました。痛みが強い日は角度や回数を減らし、息を止めないように行いましょう。
1. 朝:温度差の“当たり方”をやわらげる「起き抜けルーティン」
目的:交感神経に偏りすぎない立ち上がり/首肩の過緊張をほどく。
手順
1)起床後すぐに白湯を一口、首元を薄手のマフラーやタオルで保温。
2)椅子に浅く座り、鼻から吸って口から長く吐く×5呼吸。
3)肩甲骨の大きな回し(前→上→後→下)×10回+首の側屈ストレッチ(左右各10秒×2)。
注意点:痛みが増す角度は避ける。めまい・吐き気が強い日は無理をしない。
所要時間:2〜3分。
(同じ姿勢を避ける・体操・温めは一次性頭痛の基本対策です)
2. 日中:30〜45分ごとの「こまめ姿勢リセット」
目的:緊張型の要因である首肩の持続緊張と目の酷使をこまめに断つ。
手順
1)タイマーを30〜45分で設定し、合図で立ち上がる。
2)壁に背をつけ、後頭部・背中・骨盤をそっと壁へ(反らしすぎない)。
3)壁天使:肘と手の甲を壁に沿わせて上下×5回。
注意点:腰を反らさない/肩をすくめない。
所要時間:1〜2分。
(生活リズムの整備と姿勢配慮は対策として推奨されます)
3. 夜:入浴+光と音を落とす「クールダウン」
目的:自律神経の切替えを促し、翌朝のこわばりを軽くする。
手順
1)就寝1〜2時間前にぬるめの入浴10〜15分。
2)湯上がり後は照明を落として深呼吸×5〜8呼吸、スマホの光は遠ざける。
3)椅子に座って側頭部〜耳の周りをやさしく円を描く→首の付け根を温める→肩回し×10回。
注意点:のぼせ・持病がある方は医師の指示に従う。片頭痛発作中は光・音刺激を避け、暗く静かな環境で休む。
所要時間:入浴含め15〜25分。
(片頭痛のケアでは静穏環境・生活リズムの調整が重要です)
室温は急激に上げすぎず、外出前後は首元・肩甲帯の保温で温度差のギャップを小さくすることがポイント。衣類の重ね着や首周りの保温は、実際の気温差を体が受け取る強さをやわらげます。
よくある質問(FAQ)
受診の目安は?
A. 次のようなときは医療機関へ:突然の激烈な頭痛、神経症状、発熱や項部硬直、外傷後、50歳以降の新規頭痛、妊娠・産後の新規頭痛など。ガイドラインのSNNOOP10が参考になります。
どんな人に向いていますか?
A. 外気と室温の寒暖差で「頭が重い」「こめかみがズキズキ」「肩首が固まる」などの方、自律神経・脳疲労や姿勢の視点で、強刺激に頼らないケアを希望される方に向いています。
6) まとめ
- 秋〜冬は外気と室温の寒暖差や気象変化で自律神経に負担がかかり、緊張型頭痛や片頭痛が悪化しやすい季節です。
- 予防の基本は温度差の当たり方を小さくし、姿勢リセット・入浴・呼吸などで日々のリズムを整えること。
- 無理は禁物。小さな習慣を積み重ねることが、からだを守るいちばんの近道です。つらい時は早めに相談してください。
**お困りの方は 【電話】または 【LINE公式】へ。インターネット予約も承ります。「まずは相談だけでもOK」です。お気軽にどうぞ。
【監修:柔道整復師 神田博行】
参考文献
厚生労働省関連資料『一次性頭痛と生活対処(室内・衣服の調整、睡眠・活動の整え)』ニュースレター資料。https://www.kenkomie.or.jp/file/newsletter/k_202209.pdf
日本頭痛学会『かけはし No.3:天候と頭痛の関係』(天候・気象要因と頭痛の関連)。https://www.jhsnet.net/pdf/kakehashi_No03.pdf
日本頭痛学会『頭痛の診療ガイドライン2021』(一次性頭痛の診断・誘発因子・SNNOOP10 ほか)。https://www.jhsnet.net/pdf/guideline_2021.pdf
国立国際医療研究センター/厚生労働省監修 eJIM『頭痛(片頭痛・緊張型頭痛)』一般向け解説。https://www.ejim.mhlw.go.jp/pro/overseas/c05/12.html